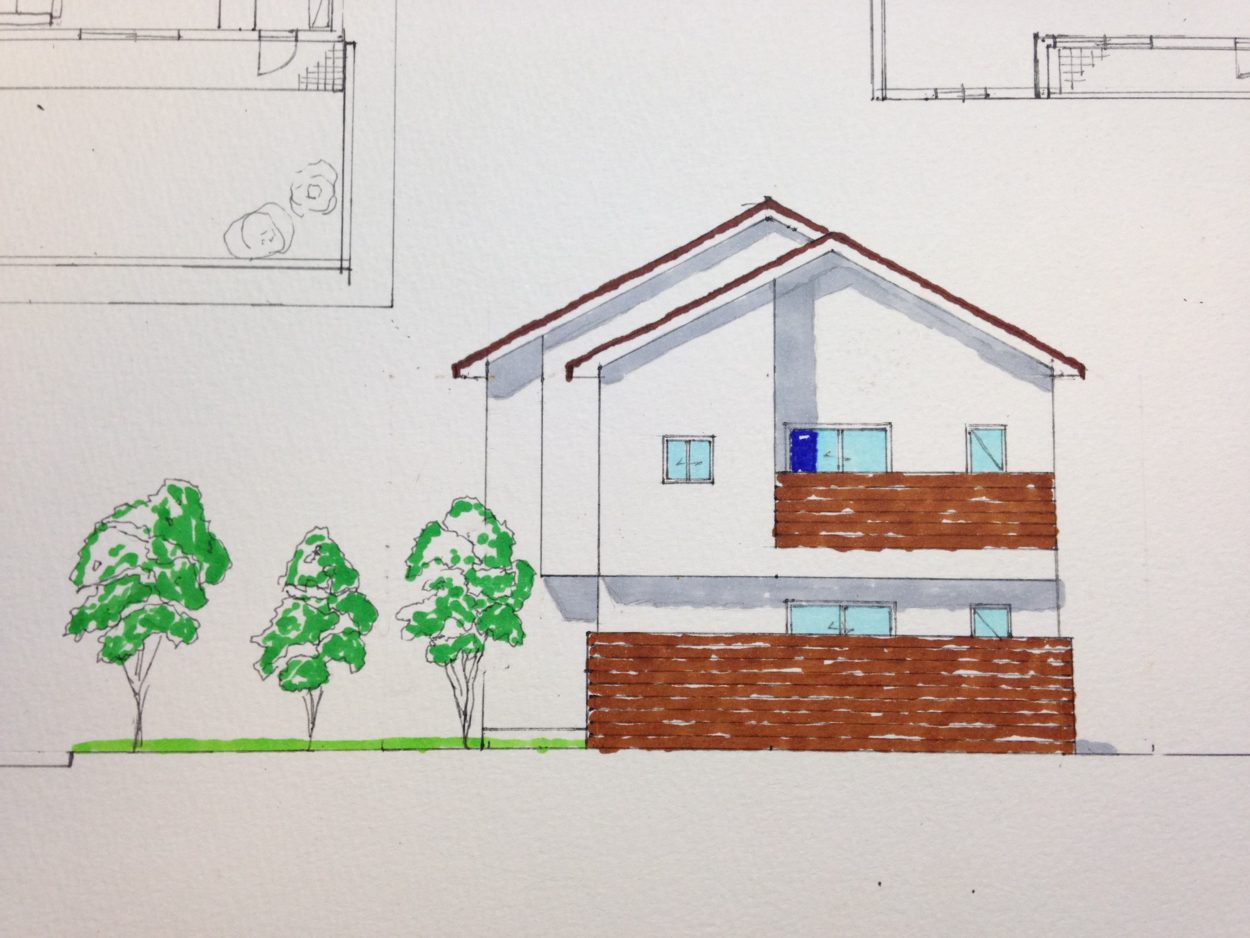こんにちは!もやしです。
丸の内建築の見学ツアーに参加してきました。
このツアーはAGCが主催していて、最新のガラス工法を使用した建築や商品を紹介してくれます。
また、CPD制度も行っているので、建築士の方にも価値のあるツアーだと思います。

施設内にある展示商品。
住宅やオフィスで利用出来る調光ガラスです。微弱電流を流すことによって、透明だったガラスの光の透過率を低下させています。

このような感じで曇りガラスのようになります。
微弱電流を流すのはガラス内の物質を変化させている間だけのようで、継続的に電力を使う事はないとの事です。
オフィスの会議室やビルの外装には多く採用されています。
住宅では、襖の代わりに利用したら面白いのではないかと感じました。

ツアーでは東京駅周りの実物件を見学しました。
東京駅の八重洲北口エントランスには、DPG(Dot Point Glazing)構法が採用されています。テンポイント構法とも言われるとの事。

DPG構法は、1枚のガラスの四隅に穴を開け支持金物を差込み、金物を介して方立により支持する構法です。
金物はピン支持となっている為、風や地震による建物の揺れに追従することなく、揺れのエネルギーの流れを遮断することができます。
ガラスに穴を開けるため、一般的に急速冷却を行う強化ガラスが使われています。その工程で、写真のような小さな歪が生じてしまうようです。

東京駅のDPG構法では、縦方向の動きは方立、横方向の動きには吊りワイヤーを使い自由に変形出来るようにしているように見えました。

丸の内北口ビルディングのピロティファサードです。
ここでは先程のDPG構法とは違い、メタルポイント構法が採用されてます。
メタルポイント構法は、ガラスを挟み込むように鋼製金物を取付け、方立により支持する構法です。金物は、DPGと同じくピン支持となっており自由に動きます。
利点は、DPG構法とは違いガラスに穴を開けなくて良いので強化ガラスとする必要がないことです。
上の写真では、方立が上部から吊っているだけのガラスマリオンとなっています。吊りガラスだけで、ガラスのカーテンを持たせているので、壊れそうで怖いです。

場所は違いますが、メタルポイント構法を背後から撮った写真です。支柱(方立)から伸びる金物はピン接合になってると思います。

余談ですが、東京駅八重洲口側のガラス手摺。
奥まで真っ直ぐ通ってます。スーパーゼネコンの技術力は凄いなと思います。
 高層ビルのカーテンウォール。
高層ビルのカーテンウォール。
よく見るとスラブ部分のガラスの色が違います。
耐火建築物は水平区画をするため、ガラスの側面の隙間を塞ぎ耐火性能のある部材で塞ぐ必要があり、ガラスに耐火ボードを貼り付けています。

東京国際フォーラムにある東京メトロ駅出入り口のガラス庇。
構造体はガラスとテンポイントのみでつくれています。
日本は地震大国であることからガラスの構造体の信用性が余りないようで、唯一のガラス構造体造作物だそうです。

ガラス庇を支える骨格部分。
緑がかった両側のガラスの間に2枚のアクリル板が入っています。
構造計算上はガラスでも持ちますが、瞬間衝撃がかかった時を懸念し割れにくいアクリルを挿入しているそうです。
まとめ
東京駅・丸の内周辺をツアーとして歩いてみて、都内には多くのガラス建築があり、歩いてるだけでも勉強できるものがたくさんあると感じました!
やはりより深く学ぶためには最低限の知識をもっていることが大切で、そういった意味でこのツアーに参加したことで、違った視点でガラス建築を見ることが出来そうです。
皆様もぜひ参加してみてはどうでしょうか。
ご精読ありがとうございました。